1月から2月にかけて映画観るぞ観るぞ月間をやっていたんですが、3月に入ってえらい失速してしまいました。
その中でも、これだけは観ておきたい、と思った映画。
それが、この「関心領域」です。
- 監督:ジョナサン・グレイザー
- 脚本:ジョナサン・グレイザー
- 出演:クリスティアン・フリーデル、ザンドラ・ヒュラー、ラルフ・ハーフォース、マックス・ベック
- 上映時間:105分
- 公開日:2024年05月24日
映画「関心領域」とは
空は青く、誰もが笑顔で、子供たちの楽しげな声が聴こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から黒い煙があがっている。時は 1945 年、アウシュビッツ収容所の所長ルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)とその妻ヘドウィグ(ザンドラ・ヒュラー)ら家族は、収容所の隣で幸せに暮らしていた。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わす何気ない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らとの違いは?
「関心領域」/Filmarks
なぜそう呼ばれていたのか、なぜそういう名前がついたのか。
ナチスはアウシュビッツ=ビルケナウ収容所の周辺40平方キロメートルの範囲を「zone of interest」と名付けたのだそうです。
このブログを書くにあたって、ホロコースト──ナチスドイツ政権を主としたユダヤ人虐殺について少し調べたのですが、どんどん気持ちが落ち込んでくる。
少し、でこれほどまでに落ち込むんだから恐ろしい。
でも目をそらしちゃいけないことなんだよなあ、こんなことが現代で怒ったら怖いなあ、嫌だなあ、という気持ちで様々なWEBサイトを見ました。
「関心領域」は、ホロコーストの代名詞と言えるでしょうか、通称アウシュビッツの所長を務めたルドルフ・フェルディナント・ヘスとその家族の、端的に言えばホームビデオのようなものです。
塀の向こうには、現代に生きる私たちなら、さほど詳しくなくてもなんとなく知っている、あのアウシュビッツ収容所がある。そしてそこで何が行われているか、ヨーロッパから遠く離れた日本に住む私たちは知っている人の方が多い。
ある種の異常の中で、それでも流れる映像は田舎暮らしを楽しむ妻と仕事に追われる夫、そして楽しそうな子供たちが暮らす庭の広い家でのホームドラマが流れ続けるのです。
「関心領域」感想(ネタバレもあり)
ルドルフ・フェルディナンド・ヘスといえばナチスの将校でありホロコーストの戦犯として敗戦後、絞首刑となった人物です。

※Wikipediaページにはややショッキングな画像が含まれていますので、閲覧にはご注意ください。
ナチの戦犯と言えば極悪非道で、人の心がなくて、残虐で……みたいな印象を持ってしまうのですが、「関心領域」で描かれるヘスの姿は、家庭のことや子の成長や、仕事に悩むよき父のように見えます。
最初は。
たぶん、「知っている」人であれば、このホームドラマの異常さに徐々に気付き始めるのではないでしょうか。
そもそも、塀を隔てた向こうでは1日に想像もつかない数の人間が「処分」されている。
そして、この平和で豊かな庭を持つ家で暮らす家族や使用人たちは、そのことを「知っている」。
ダイヤが隠されていたと言っては「収容所」から歯磨き粉を取り寄せる女性、押収した毛皮を羽織り、ポケットに入っていた口紅を当たり前のように使う妻、落ちていた歯を集めて遊ぶ子供。
何が起きているのは知っているけれど、彼らにとって塀の向こうで「処分」されているのは人間ではなく「荷」なのです。
関心がないのは知らないのと同じ。
冒頭の数十分間は、とにかく退屈で眠たくなる映画だな……という感想でした。
だって平和に暮らす家庭のホームドラマなんだもの。
けれど、徐々に異変は起こり始めます。
というか、最初から異変は置き続けているのです。
背景に立ち上る煙。
ずっと流れ続けている銃声、怒号、悲鳴や何を言っているか分からないが恐らく懇願の声。
それを知りながら、妻はこの家での生活を理想のものとし、夫が異動の辞令を受けた際には取り乱し、怒り、単身赴任をしろと夫を責めるのです。
この家は、というか環境はやはり異常で、子供達には何らかの問題が起きていて。
先に述べた捕虜たちの歯で遊ぶ子供、収容所から聞こえる声に呼応する子供、夜中に家の中を徘徊する子供、そして泣き止まない赤ちゃん。
「関心領域」というタイトルは、映画を観た私たちに対する問いかけのようにも思えます。
そうはいっても、なのですが。
東京から1万km以上離れた場所で起きたことを、いくらインターネットが普及し世界各地で起きたニュースをリアルタイムで摂取できる現代とはいえ、そこまで気に掛けることができるかな。
実際問題、今起きてる様々な問題や戦争や、いろんなことを知ってはいるけれど、抱く感想は「こわいなあ、大変だなあ、早く解決するといいなあ」くらい。
この映画に関して無関心はよくない! という感想を見ることが多かったのですが、それはその通りだと思います。
でも私自身は、基本的には劇中に出てきたヘスの妻の母(ヘスの義母)の立場と何ら変わらないと重いっています。
平和で豊かな娘の家へ遊びに来たけれど、夜通し立ち上る煙突からの煙や銃声、悲鳴に耐えかねて、書置きだけを残して家を去った母。
掃除婦(あえてこの表現で)として勤めていた家の人間が収容所へ連れて行かれたと知り、「あのカーテン気に入っていたから欲しかったのに」という母。
私が持つ「関心」は、おそらくこの程度のことだと思います。
「東京ステッキガール」の感想の時にも書いたのですが、仮に自分が渦中にいたとして、もし自分がヘスの妻だったとして、押収した毛皮のコートやポケットの中の口紅を「気持ちが悪い」「人道に悖る」と当事者へ返せるでしょうか。
収容所の人たちが少しでも植えないようにと、リンゴを土手に埋めることができるでしょうか。
現代人から見ると歪んだ価値観を、当時の時代背景の中で「間違っている」と言えるでしょうか。
絶対無理。だって死んじゃう。殺されちゃうから。
いつかは死ぬからいいじゃんとは言ったって、そんな殺され方は嫌だから。
そういうのが、この映画の「言いたかったこと」なのかなあ、と思っています。
そして余談を
このお話の中で群を抜いて怖かったのは、妻のヘドウィグだと思います。
「やばいなこいつ」と思ったのは、夫のルドルフ・ヘスがオラニエンブルグへ赴任すると聞かされた時の反応。
自分はここを離れない、子供たちには最適の環境(マジか?)、ヒトラーへ訴えろ(正気?)、行くならあなただけで行け、と言い切り、渋々ながらもそれを承諾した夫へ、「あなたと離れるのが寂しい」と……。
怖すぎる。
典型的なヒステリーだとは思うのですが、自分で単身赴任をいいつけておいてこの変わりよう。
あとは川に灰と遺骨が流れてくるシーン。
気付いたヘスが、川遊びする子供を慌てて川から上げ、家に着くなり使用人と母親が狂ったように全身をくまなく洗い上げます。目の中まで。
最初はなんかやばい物質でも流れてたのかな? と思ったのですが、アウシュビッツから流れてくる遺灰だったんですね。
そして、おそらくユダヤ人(囚人なのかな)と関係を持ったヘスが、丁寧に局部を洗うシーン。
彼らが、収容された人間たちをどのように扱っていたのかがよくわかるシーンでした。
私がこの家に住んだら、きっとヘドウィッグやその母のような振る舞いをするのだと思います。
人間とはそういうもの、とつきつけられたような気持になりました。
あと、エンドロールがめちゃくちゃ怖かったです。
映画館で観た人が「エンドロールは最後まで観る派だけど席を立った」とか「席を立って逃げたくなる気持ちも分かる、今回は許せる」って感想を持ってるのをちらほら見かけたのですが、これは致し方ないと思います。
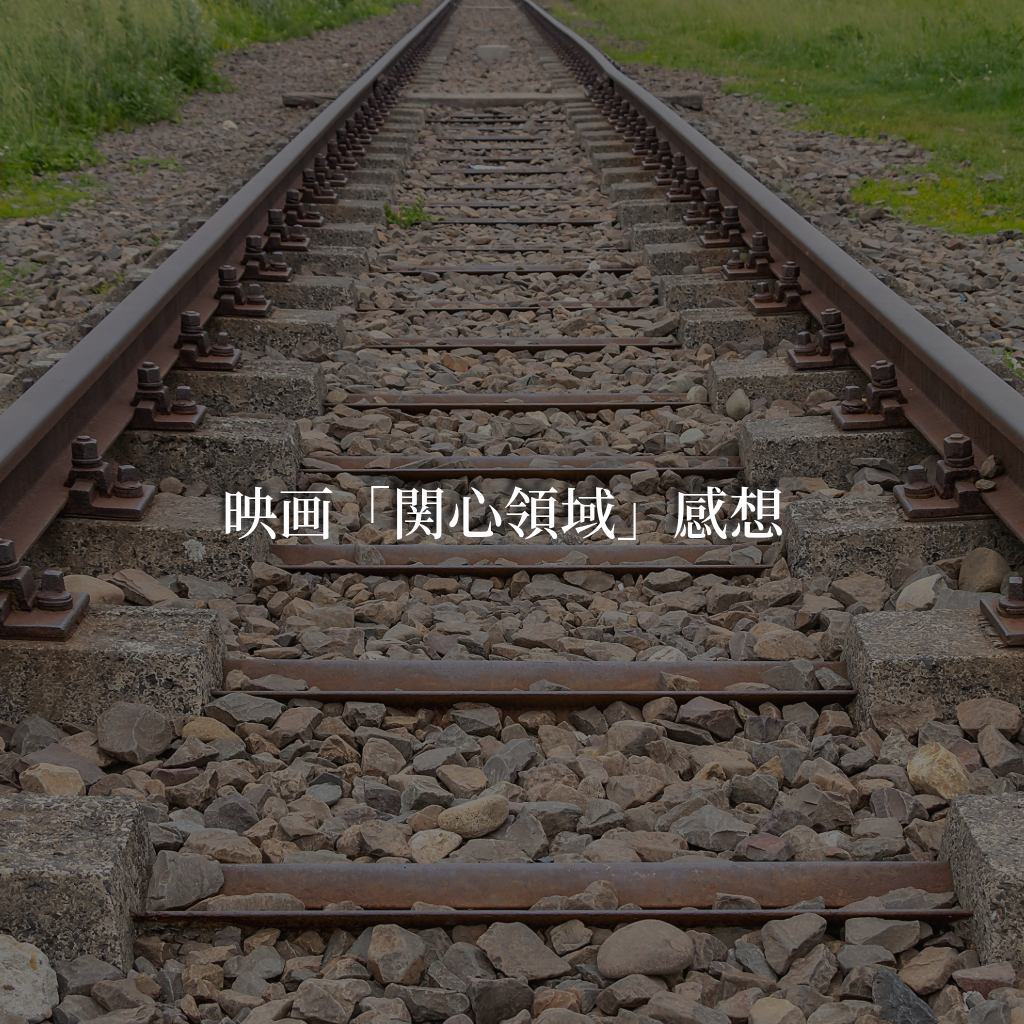




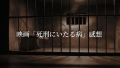
コメント